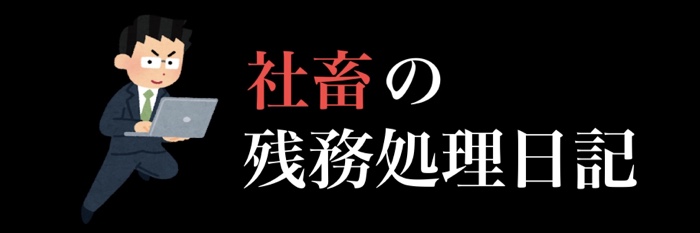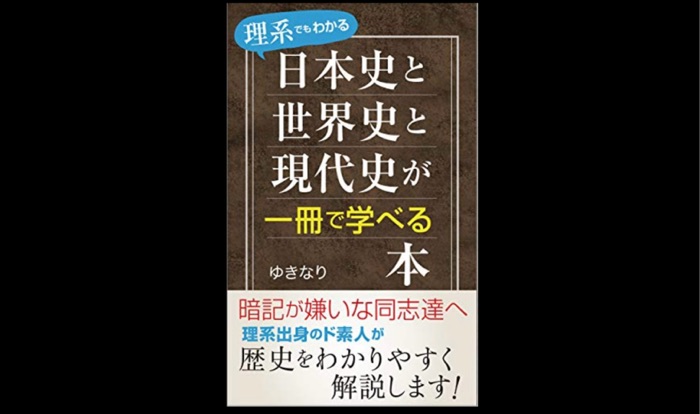何故アラサーになった今、歴史を学ぼうとしたのか
それは一般常識を知るためだ
お恥ずかしながら、僕は「歴史」を知らない
誇張ではなく本当に知らない
有名人物の名前や出来事は聞いたことがあっても、何を意味するのか全くわからないのだ
思えば中高時代に1番興味がなかった科目が社会(特に歴史)である
大人になり、歴史は一般常識として知っておくべきなのでは?と危機感を感じ続けて現在に至る
〇〇
本書を読んでみて思ったが、歴史って面白い
小中高の頃は、歴史を自分ごととして捉えられず(意味のわからない文字の羅列にしか見えない)、ただただ単語を暗記するだけの作業だった
そんなのは当然つまらないし、内容に興味を持てなかったのだろう
歴史を学ぶことは、現在の世界情勢や人類について学ぶことに等しい
それに気付いた瞬間、自分の見る世界(視野)が広がっていくのを感じたのだ
この本を読み終えて真っ先に思ったのは、戦争(内紛含む)は残酷で悲惨だということ
現在、イスラエルやイラン、アメリカ、中国、ロシア、ウクライナ等、第三次世界大戦が始まってしまっていると言っても過言ではないのかもしれない
起きた戦争はどうすることもできないのだが、世界が平和であって欲しいと、今まで以上に願うようになった
また、歴史全てを通してみると、人間というのはいつの時代も本質は変わらないのかなと思う
権力争い、下剋上、政治不満、課税、交渉、裏切り、労働 等・・・
「歴史は繰り返す」とよく言われるが、本当にそうなのだろうなと益々実感した
〇〇
以下、自分用の忘備メモ ※乱文注意
○日本史
石器、縄文時代(紀元前10万年〜紀元前300年)
二足歩行になり両手が使えるようになったので火を扱うようになる
脳の容量も増えて言葉を喋るようになった
日本列島はユーラシア大陸であり陸続きだったが、氷河期終了(気温上昇)で分裂し島国となった
島国で周りに敵がおらず、自然豊かで食物も豊富だった。このため争いも起きず、和を重んじる穏やかな日本人気質が形成されたと考えられる
現在の人類(ホモサピエンス)は3〜4万年前から海を渡ってきたと言われている(その時代の遺跡が多く見つかっているため)
弥生時代(紀元前300年〜紀元250年)
中国から稲作が伝わり、農作業が始まる
その日暮らしだったそれまでと違い、米を貯蓄(長期保管)できるようになったため、稲作(貯蓄)が上手い者とそうでない者で貧富の差が生まれるようになった
また集団作業が必要なため、指示を出すのが上手い人(リーダー)などの役割が生まれ、格差社会が形成され始める
クニという集団が形成され、クニ同士で備蓄を奪い合う争いも生まれる
卑弥呼が治める邪馬台国(今の九州か近畿地方)が有名
→現代社会の「会社」と同じ構図に見える。異なる点は現代は農業だけでなく、多種多様な業種が存在すること。現代においては同業間は競争だが、それ以外は競争でなく、社会全体がより豊かになるための分業と言える
古墳時代(250年〜600年)
奈良周辺に大和政権が誕生し、九州から関東までを支配していた※初代天皇 神武天皇
朝廷が政権を握る(皇族、貴族、豪族)
朝廷内での権力争いは先の時代まで長く続く
→昔は皇族が政治を行なっていたのか
飛鳥時代(600年〜710年)
朝廷が奈良の明日香村に遷都し、飛鳥時代が幕を開ける
中国と交流し、文字や仏教を取り入れた
日本に昔からある「神道」を広めたい物部と先進国中国の「仏教」を広げる派の蘇我で対立が起きる
神道は古くから日本で信じられている。教祖などはおらず、生活の中で自然発生した宗教。あらゆる自然物には神が宿っており、神に対して日々感謝するという考え。神社で神を祀る
仏教はあらゆる欲を捨てることで苦しみから解放されるという宗教。インドのブッダが悟りを開いて人々に伝えた。
国策では仏教を広めたが、神道は廃れずミックスされる形で浸透していった
中国の政治制度を参考に整備を進める
豪族の土地を回収して農民に配り、土地を使わせる代わりに税(米や特産物)を納めさせた(公地公民)
皇族と貴族が権力争いをしていた
→いつの世も権力争い、資源の奪い合いは絶えないんだな
奈良時代(710〜794年)
税が高すぎて平民は貧しい生活を強いられた
改善のために、一定以上の税さえ払えば土地を開拓しても免税されることになった
→今の時代(2025年)を1000年後に歴史として振り返ると、「庶民は増税や少子高齢化で苦しい生活を強いられた」と記載されるのだろうか?それとも誰でもそれなりの生活ができる良い時代と描かれるのだろうか?
平安時代(794〜1185年)
災害や伝染病から立ち直るために天皇は仏教を頼った。結果、奈良は仏教勢力が強くなったので、皇族中心政治に戻すため、平安京に遷都される(京都)
農民が土地を自由に開拓できるようになったが、法整備されてないので自分たちで守る必要があった
こうして自らを武装する農民(武士)が誕生する
皇族でもあり武士でもある源氏が政権を握る
→相変わらず権力争いは絶えないんだなと(2回目)
鎌倉時代(1185〜1333年)
鎌倉幕府が誕生する。それまでは近畿地方中心だったが、関東にも力が集まり始める。
鎌倉幕府は武士がいて力があるため、西は皇族、東は鎌倉幕府が政治を行う構図になった
天皇はこれが面白くなく、武士たちに幕府を滅ぼすよう命令したが、色々あり天皇側が負けて幽閉された
幕府は勝ったが、この後中国が攻めてきて大変なことに。運良く嵐が来たりして勝利することができた
幕府は武士たちに見返り(土地)を与えることができず、不満。これに目をつけた後醍醐天皇が武士に接触し、幕府を滅ぼさせた
→今では関東が栄えているが、この頃までは関西の方が中心地だったんだなぁと。
室町時代(1333年〜1467年)
鎌倉幕府が滅び、天皇中心社会に戻った。武士たちはまたもや貧乏な生活となり見返りもなしで土地も奪われた
不満が溜まったので室町幕府を作ることにした
幕府を作るには皇族の許可が必要なので、足利尊氏が現天皇と争っている皇族に許可をもらい設立
→幕府を開くにも皇族の許可が必要なので、皇族の誰かを味方につけないといけないようだ
戦国時代(1467〜1603年)
内乱で室町幕府が弱体化して、地方の豪族達がそれぞれの地区を仕切るようになっていく
統率力指導力が上がり、将軍と名乗るものが続々と出始める
室町幕府の足利が、当時勢いのあった将軍織田信長を頼る
幕府再興をしたが、織田が実質トップとなり不満を持った足利が、織田を暗殺しようとするが返り討ち(島流)にあう
織田は天下統一目前で部下の明智光秀に暗殺される
その後、部下の豊臣秀吉が織田信長の仇を取って明智を暗殺する
その功績とコミュ力で上り詰めていき、天下統一を果たす
豊臣秀吉の死後、徳川家康(土地持ちの大名)と石田三成(豊臣家)2人で政権を握るが対立し、徳川が勝利する
→2人以上で最後まで政治を行なった例はないのか…?権力者が複数いると対立し、殺し合いは避けられないのだろう
江戸時代(1603〜1868年)
平和な時代
個人に自由な商売を許可したので江戸に城下町ができる
徳川家康が江戸幕府を開き、各地に親族の役人を配置して裏切りを防止した
そして実力主義は裏切りや下剋上が起きるので、無能でも長男が継ぐ という風潮に変えた
大名の財力を削減し下剋上させない策略で、嫁子供を人質に江戸と地方を交互に行き来させた(参勤交代)
→これは現在の大手企業の全国転勤、単身赴任制度に似ている気がする
寺子屋が開かれ学問(教育)も重視されると同時に、武士の技術は武道に昇華させ、文武両道という概念が良いとされた
国民全体の教育水準が上がることに
キリスト教徒による一揆などが起こって面倒臭かったので鎖国し、仏教を広めようと力を入れる
しかしペリー(アメリカ)が来航し半ば強制的に鎖国は終わる
関税に関してアメリカやフランスなどに不利な関税条約を結ばされ、国民の幕府への不満はますます高まる
そして朝廷が実権を握るべきと考えた薩摩藩、長州藩が坂本龍馬の調整で協力し、討幕に成功。幕府は天皇に実権を返還した
明治時代(1868〜1912年)
イギリスから鉄砲を輸入。刀の時代は終わる
欧米列強に追いつくための富国強兵、産業教育の実施(明治維新)
安定税収のため、税を米からお金に変えた
富国強兵で国をまとめるため、地方分権型から中央集権型にした(土地や人民も天皇のものに)
地方側の藩士は土地や財政、法の管理権を失い不満。薩摩藩は政府へ戦争を仕掛ける
鉄砲で蹂躙。刀では太刀打ちできず誰も政府に逆らわなくなる
朝鮮で農民反乱が起き、清(中国)へ助けを求める。日本も人を派遣
鎮圧後も在留し続けたら、清(中国)と戦争になり、勝利(大国中国に勝つとは誰も思わなかった)
中国から賠償金を取り、製鉄所などを作って富国強兵を進める
朝鮮と中国の間にある島を領土にしたが、ロシアもそれを狙っており日露戦争が起きる
利害一致した強国イギリス(ロシアのアジア進出で中国やインドにある植民地の利益が減るリスクを考えた)と同盟を結ぶ
10倍の戦力差を覆し勝利
軍部が力をつけるまでは、戦争において深追いせず、ある程度勝ったら講和に持ち込んでいた(短期決戦)
富国強兵の副作用で公害が発生したが、反対すれば政府に処罰された
大正時代〜第二次世界大戦まで(1912〜1945年)
第一次世界大戦、第二次世界大戦など世界規模の戦争時代
日本は個人の財産没収や徴兵できる法律が定められていた
⚪︎世界史
インド カースト 奴隷階級で上位への反乱を防ぐ
ジャンヌダルク 神の啓示を受けフランスの勝利に貢献する。田舎娘がなぜこのような地位に。どのような流れでそうなったのか不思議
日本も海外も歩んできた歴史はほとんど同じな印象。宗教や国王が権力を持ち、奴隷や平民(日本の場合は武士など)から反乱が起きたり
カトリック→貯蓄は罪、稼いだ金は全て教会に寄付しなさい という考えから労働モチベ低下して衰退していく。※全盛期大航海時代が続かなかったスペインやポルトガルなど
ピューリタン→聖書重視。禁欲と勤労に専念することが大事で労働対価の所有(貯蓄)が認められ人々は一生懸命働いた ※イギリス、アメリカ、ドイツ
イギリス産業革命→産業(蒸気機関車、工業etc)が次々と発展していく。機械を使って商売するもの、使われる者の格差が開いていく(資本主義)
アメリカ独立→イギリスからの移民とその他
ファシズム→個人の自由や幸福より、自国の利益を優先する考え (第一次世界大戦後の日本、ドイツ、イタリア)